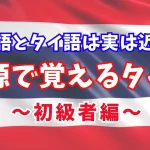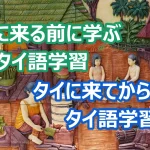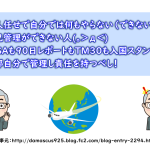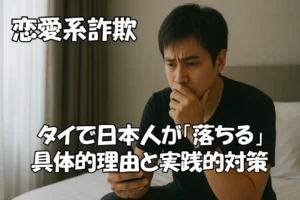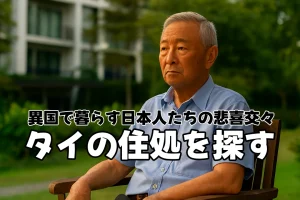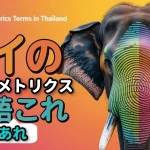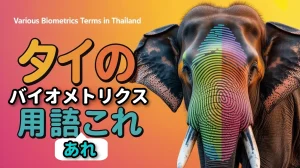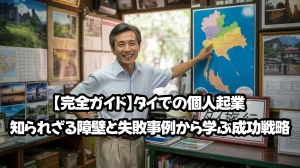はじめに:人治国家と法治国家の概念整理
タイが「実質人治国家」と呼ばれる背景を深く理解するためには、まず「法治国家」と「人治国家」という二つの対照的な統治概念を明確に区別することが不可欠である。
法治国家とは、政府を含む全ての個人が、公に開示された法規範と手続きに等しく従うことを基本原則とする社会を指す 。この体制下では、政府の行動は恣意的な意思ではなく、法によって厳しく制約される 。その主要な原則には、国民の基本的人権の保障、恣意的な権力に対する法の優越、そして「法は情熱なき理性」であり、個人の支配よりも優れているという思想が含まれる 。法治国家は、国民が安心して暮らせる安定性と予測可能性の高い環境を整備することを目指す 。しかし、単に法律が存在するだけでは不十分であり、「悪法も法となる」という問題点が示唆するように、法律が悪用されたり、国民の主権や基本的人権に反する場合には、その正当性が問われる 。法は最低限の基準を定めるものであり、法で規制されていなければ何でも許されるわけではなく、良心や理性、道徳に基づいた行動もまた重要である 。
対照的に、人治国家は、統治が確立された法規範ではなく、支配者、政権、または特定の個人の集団の個人的な意思、欲望、または気まぐれに恣意的に基づくシステムである 。この統治形態は、説明責任の欠如と、支配者ごとに規則が変化する特性によって特徴づけられる 。人治国家は、立法機関、司法機関、および法的行政・執行システムが実質的に機能しないこと、すなわち「無法状態」と関連付けられることが多い 。歴史的には、プラトンが悪法よりも優れた統治能力を持つ「例外的な人物」の支配を擁護した例もあるが、人間の本質が示すように「権力は腐敗し、絶対的な権力は絶対的に腐敗する」という現実がしばしば立証されてきた 。人治国家の支配者は、その行動の理由を説明する義務を負わず、単に「野蛮な欲望」に基づいて行動する場合がある 。
タイが「実質人治国家」と呼ばれるのは、このような法治国家の原則が形骸化している現状を指し示す。
憲法や法律といった形式的な枠組みは存在するものの、その実際の運用においては、強力な個人や集団の恣意的な行動によって法が頻繁に侵害される。
この状況は、タイにおける「法の支配の後退」として認識され、国民の司法制度に対する信頼の喪失につながっている 。これは、法が全く存在しないというよりも、法が選択的に適用されたり、無視されたりするという、法的な建前と実態との間の深い乖離を示すものである。法が単に権力者の道具として利用され、恣意的に制定・執行される場合、その正当性は失われ、形式的には法治国家であっても、実質的には人治国家の様相を呈することになる。
| カテゴリ | 法治国家 (Rule of Law) | 人治国家 (Rule of Man) |
| 根拠 | 公開された法規範、憲法 | 個人の意思、裁量、欲望 |
| 権力の源泉 | 法の優位性、国民の意思 | 支配者の力、恣意的な権力 |
| 意思決定の原則 | 理性、公平性、公に開示された手続き | 恣意性、感情、説明責任の欠如 |
| 権力への制約 | 法による制約、法の平等な適用 | 制約の欠如、権力者が法の上に立つ |
| 国民の権利 | 基本的人権の保障、平等な保護 | 不安定、不平等、権利の侵害 |
| 社会的影響 | 安定、予測可能性、信頼 | 混乱、不信、無法状態 |
タイ政治史における軍部の恒常的介入と憲法変動
タイが「実質人治国家」と呼ばれる最大の理由の一つは、その政治史に深く根付いた軍部の恒常的な介入と、それに伴う憲法の頻繁な改廃である。タイは「クーデター文化」と呼ばれる特異な現象に特徴づけられ、軍事介入が異常な頻度で繰り返されてきた 。1932年の絶対王政廃止以来、タイは20もの憲章や憲法を経験しており、これは平均して約4年ごとに新たな憲法が制定されてきたことを意味する 。
成功したクーデターのたびに、既存の憲法は通常、国民との協議なしに廃止され、新しい憲法が公布される 。この憲法の変動サイクルは、国の最高法規が安定した永続的な枠組みではなく、その時々の軍事政権の意思に従う一時的な道具であることを示している 。
クーデターが成功し、立法機関が存在しない状況下では、革命政府による布告が事実上の法として発せられ、憲法の改廃から各種法律の改正・廃止に至るまで多岐にわたる内容を規定する 。これは、権力による恣意的な支配が直接的に法として強制されることを明確に示している。
軍部による法の支配の形骸化は、クーデターを主導した者たちが、タイ刑法上は死刑または終身刑に相当する違法行為であるにもかかわらず、歴史的に処罰されることがなかったという事実に顕著に表れている 。さらに、タイ最高裁判所は、クーデターによる命令が異議なく法として執行されうると継続的に判示しており、これは違法な権力掌握を事実上正当化するものである 。このようなクーデターの制度化は 、「タイ政治の悪循環」として描写され、不安定な文民政府が秩序回復を名目に軍事支配に取って代わられることを繰り返している 。
軍部と保守エリート層は、安定した民主主義システムを意図的に妨げるように憲法枠組みを構築してきた 。例えば、2017年憲法は国王の権限を大幅に強化し 、軍部が任命する国家平和秩序評議会(NCPO)が上院議員を指名できるようにした 。これにより、首相選出において保守エリート層の影響力が確保され、いかなる単一政党も下院で過半数を確保することが困難になり、軍部が究極の権力仲介者としての役割を固める結果となっている 。
これは、法が破られた行為(クーデター)自体が新たな法の源となり、法制度自体が違法行為を正当化するために利用されるという、法の支配の根幹を揺るがす事態である。最も強力なアクターである軍部が法の上に立ち、その恣意的な意思が事実上の法秩序となることで、国民の信頼や投資家の予測可能性が著しく損なわれる。
軍部は直接的な政治介入に留まらず、広範な経済活動にも関与し、金融、資産運用、不動産、放送といった分野で事業を展開している 。軍事政権下で制定された法律は、しばしばこれらの軍関連企業の利益を優先し、参入障壁を厳しく設定することで、自らの事業に有利な環境を形成する 。このような経済的関与は、徴兵制による労働力や海外資本へのアクセスと相まって、軍内部に「貪欲、腐敗、自己肥大の文化」が蔓延していることを示唆している 。
軍部と王室の密接な相互依存関係、そして度重なる超憲法的な介入は、軍部が「並行国家」あるいは「深層国家」として機能していると評される所以である 。この「王室化された軍部」は 、民主化と平和的な政権交代を阻害し、軍の支配を正当化し、軍事目的のための資源配分において重要な役割を果たしている 。軍事介入は、単に政治的安定のためだけでなく、軍自身の経済的利益を保護・拡大するためにも行われるという側面がある。これにより、軍は中立的な国家の保護者から、私的な利益を追求する経済主体へと変質し、公的奉仕と私的利益の境界が曖昧になるという、人治国家の典型的な特徴が表れている。
| 年 | クーデター指導者/政権 | 憲法/憲章の制定・改廃 | 政治的影響 | 法の支配への影響 |
| 1932 | 絶対王政廃止 | 初の憲法制定 | 立憲君主制へ移行 | 法的枠組みの基礎確立 |
| 1947 | 軍部 | 暫定憲法制定 | 軍部支配の強化 | 憲法の不安定化、軍部の権力源化 |
| 1957 | サリット・タナラット軍事独裁政権 | 1959年憲章(独裁体制) | 軍事独裁の確立、不敬罪の政治利用 | 法の恣意的な解釈と適用 |
| 2006 | 軍部(ソンティ司令官) | 暫定憲法制定後、2007年憲法公布 | タクシン政権打倒、政治的混乱の深化 | 憲法が権力者の道具化、司法の政治化の加速 |
| 2014 | プラユット陸軍司令官(軍事政権) | 2017年憲法制定(国王権限強化、軍部任命上院) | 軍部主導の政治体制確立、民主化の停滞 | 法的枠組みによるエリート支配の固定化、法の支配の形骸化 |
王室の政治的影響力と不敬罪の役割
タイが「実質人治国家」と呼ばれるもう一つの重要な側面は、王室が持つ絶大な政治的影響力と、それを維持するための不敬罪(刑法112条)の役割である。タイは立憲君主制国家であるものの 、国王は「崇敬されるべき存在であり、侵害されてはならない」という地位を享受している 。歴史的に、タイの国王は半神的な存在として描かれ、「父性的支配」を体現し、最高行政官、最高立法者、最高裁判事として絶対的な権力を行使してきた 。1932年の革命後も、「国王の不可侵の地位」は憲法に明記され続けている 。さらに、2017年憲法は、国王が摂政を置かずに国外に出国できるなど、国王の権限を大幅に強化した 。
王室は軍部と密接な相互依存関係を維持しており、これが「王室化された軍部」や「深層国家」の形成に寄与している 。国王は歴史的に政治紛争の調停役を果たし、時にはクーデターの指導者を公然と支持することさえあった 。
この王室の地位を保護するための最も強力な法的手段が、タイ刑法112条に定められた不敬罪である。この法律は、国王、王妃、王位継承者、または摂政を中傷、侮辱、または脅迫することを違法と定めている 。不敬罪は「世界で最も厳しい不敬罪」と評され、各罪状につき3年から15年の懲役刑が科される 。この法律の解釈は広範であり、特に1957年以降は、国王が「いかなる形でも批判できない」ことを意味すると解釈されてきた 。タイは、第二次世界大戦以降に不敬罪を強化した唯一の立憲君主制国家であるという点でも特異である 。
不敬罪は、政治的反対派を抑圧し、批判的な言論を封じ込めるための政治的道具として一貫して利用されてきた 。最近の事例としては、前進党が刑法112条の改正を公約に掲げたことが、立憲君主制を転覆させようとする試みであるとして、憲法裁判所が同党に解党判決を下したことが挙げられる 。これは、法的な規定が、政治的な挑戦を排除し、イデオロギー的な同調を強制するためにどのように利用されるかを示すものである。
不敬罪の厳格な執行と広範な解釈は、国際人権法、特に意見表明の自由と相容れない 。厳しい罰則の脅威は、王室や関連する政治問題に対する公の議論や批判的なコメントを制限する萎縮効果を生み出す 。この法的メカニズムは、王室およびそれに連なる人々を、公の責任追及や法的異議申し立ての対象外に置くことを可能にし、法の支配の原則である「全ての人が法の下に平等である」という原則に直接的に矛盾する 。その結果、特定の個人や機関が「法の上に立つ」か、あるいは自らの利益のために法の適用を指示できるシステムが強化される。不敬罪は、タイにおける「人治国家」の領域を創出し、維持する上で根本的な役割を果たしている。王室を「不可侵」とし、批判の対象外とすることで、社会の一部が他の人々と同じ公的監視や法的異議申し立ての対象とならない領域を確立する。この法律の広範な解釈と政治的適用は、その目的が単に尊厳の保護にとどまらず、異議を抑圧し、エリートの権力構造を維持することにあることを示しており、権力者(王室とその同盟者)の意思が表現の自由や法的平等の原則に優先することを可能にしている。
王室の強化された憲法上の権限は 、「王室化された」と自認する軍部によって補強され 、さらに司法機関(特に憲法裁判所)が不敬罪を積極的に適用して、この確立された秩序に対する政治的脅威を排除する 。これは、これら三つの強力なアクターが連携して現状を維持し、民主主義的な空間を効果的に制限し、国民の負託や法的異議申し立てよりも彼らの集合的な意思が優先されることを保証する自己強化的なシステムを構築している。これは、制度的権力が恣意的な支配を維持するために協調する、洗練された形態の「人治国家」である。
| カテゴリ | タイ不敬罪(刑法112条)の概要 | 政治的影響 | 法の支配への影響 |
| 法的根拠 | 刑法112条 | 憲法上の王室の不可侵の地位を補強 | 法の恣意的な解釈を許容する根拠となる |
| 対象 | 国王、王妃、王位継承者、摂政 | 特定の個人を法的な批判から保護 | 法の平等原則に反し、特定の個人を法の上に置く |
| 罰則 | 各罪状につき3~15年の禁固刑 | 異議申し立てや批判を抑圧する強力な手段 | 表現の自由を不当に制限し、萎縮効果を生む |
| 特徴 | 広範な解釈、批判の禁止、世界で最も厳しい法律の一つ | 政治的ツールとして利用され、民主的プロセスを歪める | 法の予測可能性と公平性を損なう |
| 政治的利用事例 | 政治的反対派の弾圧、前進党の解党判決 | 選挙結果や国民の意思を覆す手段となる | 司法の政治化を促進し、法の客観性を損なう |
司法の政治化と法の選択的適用
タイが「実質人治国家」と呼ばれる要因として、司法、特に憲法裁判所がその本来の役割である公平な法の仲裁者から逸脱し、重要な政治的アクターと化している点が挙げられる。この司法の政治化は、法の選択的適用をもたらし、司法の独立性を損ない、法的結果が厳格な法的原則よりも政治的意図に左右される「人治国家」の様相を強めている。
1997年に憲法と民主主義を擁護するために設立された憲法裁判所は 、その意図とは裏腹に、政治紛争における主要なプレーヤーとなり、「司法の活動主義」あるいは「司法クーデター」とまで評されるようになった 。2006年のクーデター以降、司法はイデオロギー的な任命と軍部との統合を通じて、ますます政治化が進んだ 。上院は、しばしば軍部によって任命されるが、司法任命を承認する権限を持つ 。
憲法裁判所は、選出された公職者や民主的プロセスを弱体化させるために頻繁に介入してきた。例えば、2008年の人民の力党の解党や2024年の前進党への解党命令、2014年のインラック・シナワット首相の解職、2025年のペートンタン・シナワット首相の一時職務停止命令など、法的な技術論や汚職疑惑を根拠に、進歩的な政治勢力を標的としてきた 。これらの判決は、しばしば保守エリート層の派閥と連携し、有権者の意思を覆す結果となっている 。
このような司法の介入は、司法機関が独立した存在ではなく、エリート支配の政治的道具と化していることを示唆している。憲法裁判所の行動は、公正な法的判断というよりも、政治的権力闘争の延長として認識され、法の支配がその本来の守護者であるはずの機関の内部から侵食されている。これにより、法的手続きは、司法の任命と解釈を支配する者たちによる「人治国家」の手段と化している。
司法の行動は、法の選択的適用のパターンを明確に示している。法的原則は、タクシン派や進歩的な運動に属する政治的対立者を不利にする形で解釈・適用される 。このような選択的な執行は、「全ての人が法の下に平等である」という法の支配の基本的な原則を侵害するものである 。その代わりに、法的な結果が客観的な法的解釈ではなく、政治的所属やエリートの利益によって影響されることを示唆している 。このような司法介入を許す制度の改革がなければ、真の政治的安定は望めない 。
これは、保守エリート層と軍部が、司法制度を、特に司法を、自らの権力を維持し、真の民主的変化を阻止するためのメカニズムとして意図的に利用していることを示している。法は、普遍的な法を維持するためではなく、特定の派閥の利益に奉仕するために再利用され、権力者が選挙結果に関わらず誰が統治できるかを決定する「人治国家」を維持するための武器と化している。
高等司法機関だけでなく、末端の法執行機関(警察)も、広範な裁量権の行使と、腐敗と不処罰の文化を通じて「人治国家」に寄与している 。
警察官は、交通法規の執行から抗議活動における逮捕に至るまで、かなりの裁量権を行使し、その党派的な歴史と蔓延する腐敗は、市民が市民的・政治的権利を行使する上で曖昧な空間を生み出している 。この裁量権は不確実性を生み出し、警察官が個人的な偏見、金銭的利益、または政治的目標に基づいて市民の権利を擁護するか、あるいは侵害するかを決定する可能性がある 。拷問、恣意的な逮捕・拘禁、警察による虐待が不処罰で行われているという信頼できる報告は、この状況をさらに裏付けている 。このような虐待に関する調査は、解決までに何年もかかることが少なくない 。
これは、法の支配が、高位の政治から市民の日常生活にまで及ぶ「人治国家」の様相を呈していることを示している。法執行機関が大きな裁量権を持ち、個人的な偏見や金銭的・政治的利益のために行動し、その虐待が不処罰で済まされる場合、法は予測可能で普遍的な基準ではなくなる。その代わりに、個々の警察官、市民の地位、あるいはそのつながりによって変動するものとなる。これは国家に対する不信感を助長し 、権利が法によって保障されるのではなく、それを執行する者の恣意的な意思に左右されることを意味し、「人治国家」を多くのタイ国民にとって日常的な現実としている。
| 年 | 判決内容 | 対象政党/人物 | 根拠 | 政治的影響 | 法の支配への影響 |
| 2008 | 人民の力党解党 | 人民の力党(タクシン派) | 選挙違反、連座制 | タクシン派政権の崩壊、政治的混乱の激化 | 司法の政治化、選挙結果の無効化 |
| 2014 | インラック・シナワット首相解職 | インラック・シナワット(タクシン派) | 汚職疑惑 | 軍事クーデターへの道を開く | 司法による民選政府の転覆、法の選択的適用 |
| 2024 | 前進党解党命令 | 前進党(進歩派) | 不敬罪改正公約が立憲君主制転覆を企図 | 野党第一党の排除、若者層の政治参加への打撃 | 言論の自由の制限、司法による政治的排除の常態化 |
| 2025 | ペートンタン・シナワット首相一時職務停止命令 | ペートンタン・シナワット(タクシン派) | (詳細不明だが、政治的介入の継続を示唆) | 政権の不安定化、政治的対立の激化 | 司法による行政権への介入、法の支配の信頼性低下 |
広範な汚職と縁故主義の蔓延
タイが「実質人治国家」と呼ばれる背景には、社会全体に深く浸透した広範な汚職と縁故主義の蔓延がある。これらの現象は、国民の信頼を蝕み、統治を歪め、個人的なつながりや富が法的原則に優先するシステムを形成し、「人治国家」を強化している。
タイは、トランスペアレンシー・インターナショナル(TI)が発表する腐敗認識指数(CPI)において、常に低い順位に甘んじている 。2023年には、調査対象180の国・地域中108位(スコア35/100)となり、一部のASEAN諸国と比較しても著しく低い水準にある 。CPIは、贈収賄、公的資金の不正使用、公職の私的利益のための濫用、公務員制度における縁故主義、国家の私物化といった様々な公共部門の腐敗行為に対する専門家やビジネスリーダーの認識を測定するものである 。タイでは、政策決定における腐敗と透明性の欠如により、政府への国民の信頼が低下している 。汚職は、経済の低迷と生活費高騰に次ぐ、国内で3番目に深刻な問題と認識されている 。
多数の著名な汚職事件は、富と影響力が不処罰につながる可能性を浮き彫りにしている 。例えば、ロールス・ロイスの贈収賄スキャンダルでは、タイの国家機関の代理人や航空会社従業員に不正な支払いがなされたにもかかわらず、国家汚職対策委員会(NACC)の対応は「生ぬるい」と評された 。また、レッドブル創業者の孫であるヴォラユット・ユーウィッタヤーが起こしたひき逃げ死亡事件では、度重なる延期と「不公平な扱い」の訴えにより、告訴期限が切れ、訴追を免れた 。
この事件は、「富裕層の子どもたちの事件」が一般のタイ人の事件とは異なる扱いを受けるという国民の認識を強めた 。さらに、欠陥のある爆弾探知機GT200の購入スキャンダルでは、政府機関が不良品を購入し、現地の代理店は当初無罪判決を受けたものの、後に有罪判決が下された 。タクシン元首相の家族や警察署建設問題に関する汚職疑惑も存在する 。これらの事例は、贈収賄や職権乱用を犯罪とする法律が存在するにもかかわらず 、特に有力者が関与する場合には、法の執行が一貫性を欠くことを示している。これは、法が平等に適用されるのではなく、地位やコネクションに基づいて選択的に適用されるという認識を生み出す 。
汚職は経済成長に深刻な影響を与える。コストを増加させ、生産性を低下させ、投資を阻害し、公共財政管理システムを弱体化させる 。また、中小企業の発展を制限し、貧困を拡大させる 。
この問題は、ビジネスと政府の接点で特に蔓延しており、「便宜供与のための支払い」が広く行われている 。電子入札システムなどの努力にもかかわらず、公共調達プロセスは依然として談合に脆弱である 。
パトロネージ(後援)ネットワークの存続は、えこひいきや縁故主義を常態化させ、汚職対策の取り組みを困難にしている 。これは、意思決定がメリットや公共の利益に基づいて行われるのではなく、個人的な関係や不正な利益に基づいて行われることが多いことを意味し、統治における「人治国家」の明確な特徴である。
結論
タイが「実質人治国家」と呼ばれるのは、形式的には立憲君主制と法の支配を謳う憲法を持つにもかかわらず、その運用において権力者の恣意的な意思が法規範に優先する、多層的な構造的要因が絡み合っているためである。
まず、タイ政治史における軍部の恒常的な介入、すなわち「クーデター文化」が、法の支配の根幹を揺るがしている。クーデターは刑法上違法であるにもかかわらず、その主導者が処罰されることはなく、むしろ彼らの命令が最高裁判所によって法として認められるという事態が繰り返されてきた 。これは、法が権力者によって都合よく書き換えられ、その権力掌握を正当化する道具として利用されることを意味する。
軍部は、単に政権を奪取するだけでなく、憲法や制度設計(例:上院議員の任命権)を巧みに操作し、自らの永続的な影響力と、それに連なる保守エリート層の支配を確保している 。さらに、軍部が広範な経済活動に深く関与し、自らのビジネスを優遇する法を制定してきたことは、軍事介入が政治的安定だけでなく、経済的利益の保護・拡大という動機も持つことを示唆している 。これは、公的機関が私的利益を追求する「深層国家」としての側面を強化し、法の支配を曖昧にしている。
次に、王室の絶大な政治的影響力と、それを保護する不敬罪(刑法112条)の役割が、法の支配を歪めている。国王は「不可侵」の地位にあり、2017年憲法によってその権限はさらに強化された 。不敬罪は、王室に対するいかなる批判も許さず、3年から15年という重い懲役刑を科すことで、言論の自由を著しく制限し、反対意見を抑圧する強力な政治的ツールとして利用されてきた 。
憲法裁判所が不敬罪の改正を公約に掲げた政党を解党する判決を下したことは 、特定の個人や機関が法的な批判や説明責任の対象外に置かれ、国民の意思よりも権力者の意思が優先される「人治国家」の性質を明確に示している。王室、軍部、そして司法機関が密接に連携し、既存の権力構造を維持するために法の解釈と適用を協調させることで、真の民主的空間は制限されている。
最後に、司法の政治化と広範な汚職・縁故主義が、タイを「実質人治国家」たらしめている。憲法裁判所は、その設立目的とは裏腹に、イデオロギー的な任命や軍部との統合を通じて政治的に偏向し、民選政府や進歩的な政党を解党したり、首相を解職したりするなど、繰り返し政治介入を行ってきた 。これらの判決は、しばしば保守エリート層の利益に沿い、有権者の意思を覆す結果となっている 。
これは、法が公正な仲裁者ではなく、特定の政治勢力を排除し、権力を維持するための「武器」として利用されていることを意味する。さらに、警察などの法執行機関における広範な裁量権の濫用、腐敗、そして不処罰の文化は、市民が権利を行使する上で不確実性を生み出し、法が個々の警察官の恣意的な判断や個人的な利益によって変動する日常的な「人治国家」の現実を生み出している 。トランスペアレンシー・インターナショナルが指摘するように、汚職と縁故主義の蔓延は、公共部門における信頼を低下させ、政策決定や公共事業において、メリットではなく個人的な関係や不正な利益が優先される状況を常態化させている 。
これらの要因は相互に絡み合い、タイの政治システムにおいて、形式的な法の支配と実質的な人治国家の間の深い乖離を生み出している。軍部の介入による憲法の不安定化、王室の不可侵性と不敬罪による言論の抑圧、そして司法と法執行機関の政治化と汚職は、法の平等な適用、予測可能性、説明責任、そして国民の権利の保護といった法の支配の核心的原則を著しく損なう。結果として、国民の政府や司法制度に対する信頼は低下し 、政治的安定は遠のき、経済発展も阻害される。タイが真の法の支配に基づく国家へと移行するためには、これらの深く根付いた権力構造と文化規範に対処する根本的な制度改革が不可欠である。

タイの構造的ドグマは様々な要因があって成立しているため、これらが解決することはほぼ不可能のように思わます。
引用文献
- Rule of man - Wikipedia, 7月 30, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_man
- 官庁の基礎知識 日本は法治国家/ホームメイト - パブリネット, 7月 30, 2025にアクセス、 https://www.homemate-research-public.com/useful/19101_publi_002/
- A National Agenda: Driving the Rule of Law - the Importance of the Rule of Law for Thailand, 7月 30, 2025にアクセス、 https://www.tijthailand.org/en/highlight/detail/rule-of-law-forum-2024
- en.wikipedia.org, 7月 30, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_man#:~:text=Absence%20of%20rule%20of%20law%20implies%20the%20absence%20of%20a,system%2C%20that%20is%2C%20lawlessness.
- Is a Coup Coming Soon in Thailand? | Council on Foreign Relations, 7月 30, 2025にアクセス、 https://www.cfr.org/article/coup-coming-soon-thailand
- Dynamics and Institutionalization of Coup in Thai Constitution" - Institute of Developing Economies, 7月 30, 2025にアクセス、 https://www.ide.go.jp/library/English/Publish/Reports/Vrf/pdf/483.pdf
- Constitution of Thailand - Wikipedia, 7月 30, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Thailand
- タイ軍事クーデタ - 世界史の窓, 7月 30, 2025にアクセス、 https://www.y-history.net/appendix/wh1703-072_3_1.html
- Thailand: from coup to crisis - European Parliament, 7月 30, 2025にアクセス、 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659330/EPRS_ATA(2020)659330_EN.pdf
- 1. タイ法の歴史 - 国際民商事法センター, 7月 30, 2025にアクセス、 https://www.icclc.or.jp/icclc-news/102/news_102_3.pdf
- Thailand's Revolving Senate: How Constant Changes Cement Military Power | New Perspectives on Asia | CSIS, 7月 30, 2025にアクセス、 https://www.csis.org/blogs/new-perspectives-asia/thailands-revolving-senate-how-constant-changes-cement-military-power
- タイの法制度の概要 - BLJ法律事務所, 7月 30, 2025にアクセス、 https://www.bizlawjapan.com/wp-content/uploads/thailand_houseido_01-2.pdf
- The Economic Role of the Thai Military: A Commercial Logic to Coups? (Chapter 5) - Praetorians, Profiteers or Professionals? - Cambridge University Press, 7月 30, 2025にアクセス、 https://www.cambridge.org/core/books/praetorians-profiteers-or-professionals/economic-role-of-the-thai-military-a-commercial-logic-to-coups/551810B58AE994AEB34BBAC72902DAF7
- Can Thailand's Military Evolve?: Moving Beyond Domestic Interference, Institutional Corruption, and Personal Gain > Air University (AU) > Journal of Indo-Pacific Affairs Article Display, 7月 30, 2025にアクセス、 https://www.airuniversity.af.edu/JIPA/Display/Article/3606777/can-thailands-military-evolve-moving-beyond-domestic-interference-institutional/
- Lèse-majesté in Thailand - Wikipedia, 7月 30, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A8se-majest%C3%A9_in_Thailand
- アジアの「民主主義」第5章タイ―タイの今とこれから, 7月 30, 2025にアクセス、 https://www.nira.or.jp/paper/research-report/2024/382403.html
- Monarchy of Thailand - Wikipedia, 7月 30, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Monarchy_of_Thailand
- The law of inviolability in Thailand/ Thai Laws Reflecting Thai Culture and Ethics/ Lese majeste: abuse and benevolence (By Prof Dr Borwornsak Uwanno) - สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ, 7月 30, 2025にアクセス、 https://dvifa.mfa.go.th/th/content/40461-the-law-of-inviolability-in-thailand-thai-laws-reflecting-thai-culture-and-ethics-lese-majeste:-abuse-and-benevolence-(by-prof-dr-borwornsak-uwanno)?cate=5f206717170d9008ea136ad1
- はじめに タイは、東南アジア大陸部において政治経済的にも地理的にも要の地位にある。同国 - 日本国際問題研究所, 7月 30, 2025にアクセス、 https://www2.jiia.or.jp/kokusaimondai_archive/2010/2013-10_003.pdf?noprint
- Thailand: UN rights expert concerned by the continued use of lèse-majesté prosecutions, 7月 30, 2025にアクセス、 https://www.ohchr.org/en/press-releases/2017/02/thailand-un-rights-expert-concerned-continued-use-lese-majeste-prosecutions
- 憲法裁判所、前進党に解党判決(タイ) | ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース, 7月 30, 2025にアクセス、 https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/08/849f32245a40277f.html
- 憲法裁判所、前進党の不敬罪改正を求める選挙活動に違憲判決(タイ) | ビジネス短信 - ジェトロ, 7月 30, 2025にアクセス、 https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/02/8750a3b29e4ce922.html
- Constitutional Court of the Kingdom of Thailand - European Law Institute, 7月 30, 2025にアクセス、 https://www.europeanlawinstitute.eu/membership/institutional-members/constitutional-court-of-the-kingdom-of-thailand/
- The Role of the Constitutional Court of the Kingdom of Thailand to strengthen democracy and maintain harmony in society - WCCJ, 7月 30, 2025にアクセス、 https://wccj5.mkri.id/public/upload/papers/SC%20-%20Session%205%20-%20Part%202%20-%204%20-%20Srimoung%20&%20Treesomphong%20(Thailand).pdf
- ȡ!ے൮࡞!ȡ!, 7月 30, 2025にアクセス、 https://www.moj.go.jp/content/000121599.pdf
- 憲法裁判所はいかにタイの選挙の清廉性を損ねるか - Kyoto Review of Southeast Asia, 7月 30, 2025にアクセス、 https://kyotoreview.org/issue-40/thai-constitutional-court-erodes-electoral-integrity-ja/
- 「司法介入」によるタイの首相交代――誰が何を目指し動いたのか?(青木(岡部)まき), 7月 30, 2025にアクセス、 https://www.ide.go.jp/Japanese/IDEsquare/Eyes/2024/ISQ202420_029.html
- How Thailand's Street-Level Cops Use of Discretion Creates Ambiguous Access to Civil and Political Rights, 7月 30, 2025にアクセス、 https://asianstudies.confex.com/asianstudies/2025/meetingapp.cgi/Paper/16544
- 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Thailand - State Department, 7月 30, 2025にアクセス、 https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/thailand
- Police Violence - Amnesty International Thailand, 7月 30, 2025にアクセス、 https://www.amnesty.or.th/en/our-work/police-violence/
- 汚職度示す国際ランキングでタイが順位7つ下げる ネパール エジプトと同一指数 - バンコク週報, 7月 30, 2025にアクセス、 https://bangkokshuho.com/thaisocial-32/
- タイの清廉度、180カ国・地域中108位 日本16位 NGOの汚職調査 - newsclip.be, 7月 30, 2025にアクセス、 https://newsclip.be/thai-news/thai-local/9748
- From transparency to trust: Key determinants of corruption perception in Thailand - ThaiJO, 7月 30, 2025にアクセス、 https://so15.tci-thaijo.org/index.php/jamsd/article/download/1568/895
- Thailand: Experts share lessons for countering corruption - World Bank, 7月 30, 2025にアクセス、 https://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/02/23/thailand-experts-share-lessons-for-countering-corruption
- Corruption Perceptions Index - Wikipedia, 7月 30, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_Perceptions_Index
- I. Introduction II. How the Thai Public Sector is Fighting Against Corruption - OECD KOREA POLICY CENTRE, 7月 30, 2025にアクセス、 https://www.oecdkorea.org/admin/include/download.asp?fileName=202211271520%2Epdf&fileSaveName=Thailand%2Epdf&filePath=%2Fuploads%2FBOARD%5FATTACH%2F202211
- タイにおける反汚職クーデタ - Kyoto University Research Information Repository, 7月 30, 2025にアクセス、 https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/266561/1/InternationalAffairs_89_159.pdf
- Corruption in Thailand - Wikipedia, 7月 30, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_in_Thailand
- Category:Corruption in Thailand - Wikipedia, 7月 30, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Corruption_in_Thailand
- タイにおける 汚職・不正事例の 紹介と対策 - KPMG International, 7月 30, 2025にアクセス、 https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/th/pdf/2019/02/th-gjp-seminar-materials-20180426.pdf
- 東南アジア諸国の汚職防止法制, 7月 30, 2025にアクセス、 https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/UNAFEI_pub.2021_2.pdf
- Country Review Report of Thailand - UNODC, 7月 30, 2025にアクセス、 https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2019_09_02_Thailand_Final_Country_Report.pdf
皆様のご意見をお待ちしていますので、メッセージを下のコメント欄より投稿いただけると幸いです。
![]()