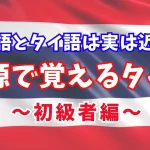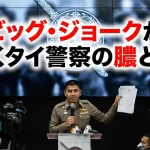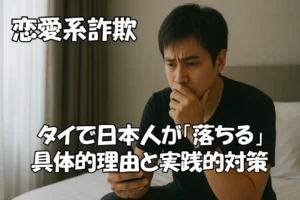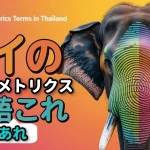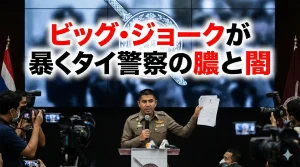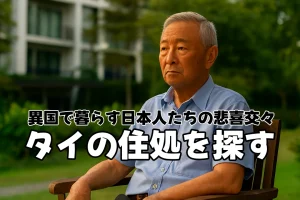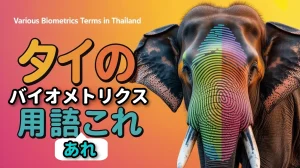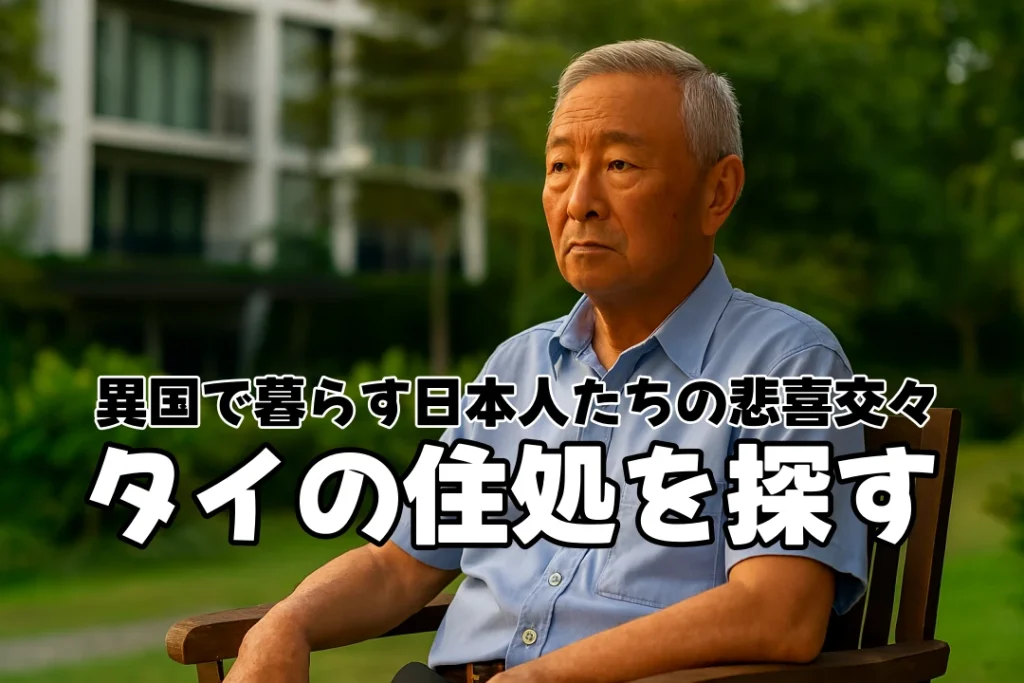
タイの住処を探す——異国で暮らす日本人たちの悲喜交々
「老後はタイで過ごしたい」「物価が安くて暮らしやすそう」「医療水準も高いらしい」——そんな期待を胸に、タイへ移住する日本人は年々増えている。だが、実際に住んでみると、そこには予想外の困難や、思いがけない喜びが待っている。「タイに移住した日本人のタイ生活」をテーマにしたNoteの記事群から浮かび上がるのは、単なる南国移住の夢物語ではない。今回は「住処」に焦点を当て、タイで暮らす日本人たちのリアルを読み解いていく。
「住む」ことは「生きる」こと——終の棲家を異国に求める覚悟
タイに長期滞在する日本人の多くは、50代以降のリタイア世代だ。彼らは日本の高齢化社会や生活費の高さに不安を感じ、タイに「終の棲家」を求める。バンコクやチェンマイなど都市部には日本語対応の病院、日本食レストラン、日本人コミュニティもあり、表面的には「安心して暮らせる環境」が整っているように見える。
しかし、実際に住むとなると、賃貸契約の条件、ビザの更新、医療費の支払い、近隣住民との関係など、生活の細部にまで目を向ける必要がある。ある記事では、1997年からバンコクに住む元医療系コーディネーターの体験が紹介されており、「住むことは生きること」という言葉の重みが伝わってくる。物件の立地や設備だけでなく、緊急時に助けを求められる人間関係の有無が、住処選びの重要な要素となるのだ。
医療と介護——制度の隙間に落ちるリスク
タイの医療水準は高く、私立病院では日本語通訳が常駐していることも多い。だが、介護サービスや高齢者向け施設の選択肢は限られており、日本のような公的支援は期待できない。記事では、脳リハビリが必要になった高齢者の事例が紹介されている。家族がいない場合、介護施設への入居や在宅介護の手配はすべて自分で行う必要がある。
また、医療費の支払いも一筋縄ではいかない。タイでは基本的に前払いが原則であり、保険が適用されないケースもある。日本の感覚で「病院に行けばなんとかなる」と思っていると、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性がある。タイに住む=老後の安心ではなく、「タイでどう老いるか」を具体的に設計する必要があるのだ。
ビザと居住権——「住める」ことと「住み続けられる」ことの違い
タイにはリタイアメントビザという制度があり、50歳以上で一定の預金があれば長期滞在が可能だ。しかし、ビザの更新には毎年の手続きが必要で、健康状態や財産状況によっては更新が難しくなることもある。記事では、長年住んでいても「永住権」が得られない現実や、病気によってビザ更新が困難になった事例が紹介されている。
また、タイの入国管理局の対応は地域や担当者によって異なり、同じ条件でも結果が変わることがある。つまり、「住み続けられる保証がない」ことが、老後の不安を増幅させる。住処を選ぶ際には、ビザ更新のしやすさや、移民局へのアクセスも考慮すべきだ。
住処の選び方——利便性より「孤立しない環境」を
タイで住処を探す際、多くの日本人はコンドミニアムやサービスアパートメントを選ぶ。清潔で設備が整っているが、隣人との交流が少なく、孤立しやすいという問題もある。記事では、「日本人が多いエリア=安心」ではなく、「助けを求められる環境」が重要だと指摘されている。
たとえば、病気や事故が起きたとき、誰が助けてくれるのか。管理人が常駐している物件か、近隣に知人が住んでいるか、緊急連絡先を共有しているか——こうした要素が、住処の安全性を左右する。物件のスペック以上に、「人とのつながり」を重視すべきなのだ。
「終活」の視点で住処を選ぶ——死後の手続きまで想定する
タイで亡くなった場合、遺体の搬送、火葬、遺品整理、遺言の執行など、日本とは異なる手続きが必要になる。家族が日本にいる場合、連絡や手配が遅れることもある。記事では、「死後の手続きまで含めて、住処を選ぶべき」という視点が強調されている。
たとえば、病院に近い場所、信頼できる知人が近くにいるエリア、遺言を管理してくれる弁護士がいる地域など、「死後の安心」も住処選びの重要な要素となる。タイでの終活は、単なる生活設計ではなく、「死後の設計」でもあるのだ。
終わりに——「住処探し」は「人生設計」の一部
タイで住処を探すことは、単なる物件選びではない。医療、介護、ビザ、死後の手続きまで含めた「人生設計」なのだ。記事に登場する高齢者たちは、「タイでどう生き、どう死ぬか」を真剣に考え、行動している。
「タイの住処を探す」というテーマは、異国での生活に憧れるだけでは乗り越えられない現実を突きつける。それでもなお、タイを終の棲家に選ぶ人々の姿には、覚悟と希望が同居している。彼らの経験は、これから移住を考える人々にとって、貴重な指針となるだろう。
![]()