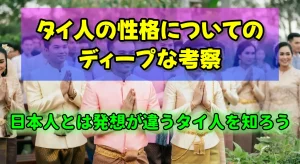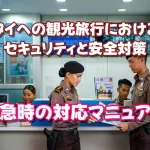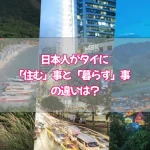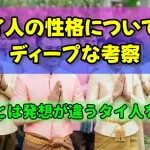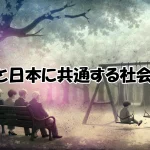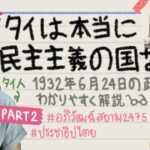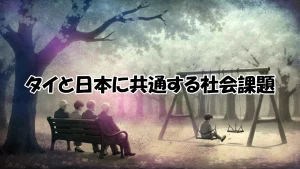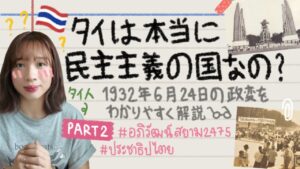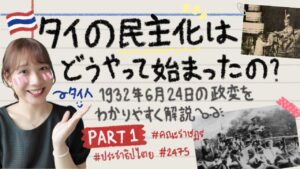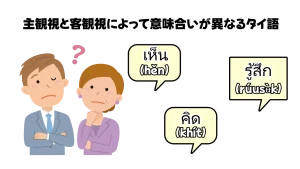タイのタンブン伝統:歴史的成り立ちと仏教的価値観の融合
タイの文化には、深く根付いた仏教の教えと独自の伝統があり、その中心にあるのが「タンブン(Tan Bun)」です。この儀式・習慣は、タイの歴史と仏教思想が融合したものであり、現代においても重要な役割を果たしています。本記事では、タンブンの歴史的背景とその仏教的意義に焦点を当て、その文化的価値を探ります。
1. タンブンの歴史的背景:仏教の伝来とタイの本土信仰の融合
タイにおける仏教は、13世紀ごろのスコータイ王朝時代に確立されました。この時期、タイはスリランカやカンボジアから小乗仏教(上座部仏教)の影響を受け、国教として採用しました。
しかし、タイの仏教は、単にインドやスリランカの仏教を模倣したものではなく、本土の自然崇拝や精霊信仰と融合し、独自の形を形成しました。
この融合によって生まれたのが「タンブン」です。タンブンは「赕布」や「赕佛」とも表記され、「布施」を意味しますが、単なる布施以上に、「功徳の積み立て」という概念が含まれています。人々は仏教の教えに従い、布施や戒律を守ることで来世の幸福や現世の繁栄を祈願します。
2. タンブンの核心:仏教的価値観の具体化
タンブンは、仏教の「三宝(仏・法・僧)」への敬意と「四摂(布施・愛語・利行・同事)」の実践を基盤としています。その具体的な形態と仏教的意義を以下に解説します。
(1)布施(dana):他者への慈しみ
- 僧侶への布施:朝の「トゥン・クアン」では、人々が僧侶に食物や衣料を提供します。これは、仏教の「布施の徳」を実践し、自己の欲を抑える修行でもあります。
- 地域社会への支援:祭りや儀式では、村全体で寺院の修復や困窮者への支援を実施します。これは「共栄」の精神を体現し、仏教の「利行」(他者の利益を第一に考える行動)に通じます。
(2)戒律(sila):正しい生活の基盤
タンブンの儀式では、戒律を守ることが重要です。例えば、祭りの期間中は飲酒や暴力を禁じ、仏教の「五戒」(殺生・盗み・邪淫・妄語・飲酒)を守ります。これは、仏教の「自律的な生活」へのこだわりを反映しています。
(3)因果(karma):行為の結果への信仰
タンブンの最も重要な思想は「因果応報」です。人々は、善意の行為(布施・祈り・戒律遵守)が「功徳」を生み、来世の幸福や現世の祝福をもたらすと信じます。この考え方は、仏教の「十二因縁」の思想とも深く結びついています。
3. タイの本土信仰との調和:仏教と精霊信仰の共生
タイの仏教は、本土の精霊信仰とも融合しています。例えば:
- 精霊への供養と仏教の布施の併存:村では、僧侶への布施と同時に家の守り神への供物を捧げます。これは、「他者への慈しみ」と「自然への畏敬」を両立させた形です。
- 祭りの目的の複合性:水灯節やボーリム節など、タイの伝統祭りは、仏教の功徳祈願と同時に収穫や雨乞いの祈願を含みます。この二重性は、仏教と本土信仰の共生を象徴しています。
4. 現代におけるタンブンの意義:伝統と現代社会の架け橋
現代タイでもタンブンは重要な役割を果たしています。例えば:
- 社会的結束力:祭りや寺院行事を通じて地域コミュニティが結束し、伝統を継承します。
- 精神的安定:人々はタンブン儀式を通じてストレス社会で心の安らぎを求めます。
- 文化の国際発信:タンブン儀式はタイ観光資源として注目され、仏教文化魅力を世界に伝えています。
5. 結論:仏教とタイ文化の共生の象徴
タンブン伝統はタイ歴史と文化の「魂」を形作る重要な要素です。仏教哲学と本土伝統が調和し、「功徳積み立て」思想を通じて人々生活を支え社会をつなぎ続けています。この伝統は他者への慈しみと自然への畏敬を基盤に現代社会でも普遍的価値を示すものと言えるでしょう。
参考文献
- 『タイ仏教史』(シーラチャンドラ著)
- タイ文化省公式サイト「伝統行事ガイド」
- 『タイの宗教と民俗』(ポール・スミス著)
このように、タンブンはタイ歴史的・文化的アイデンティティ形成する重要な要素であり、仏教価値観が現実生活に深く根付いていることを示す例です。
![]()