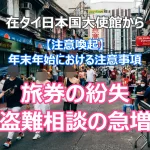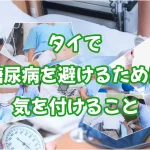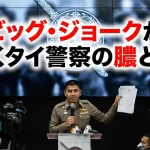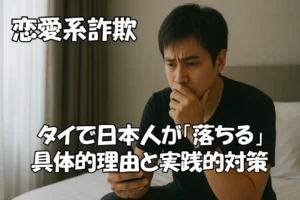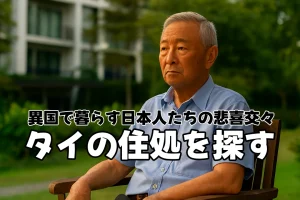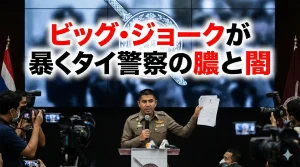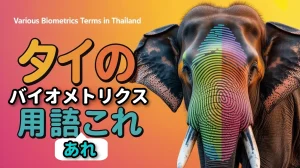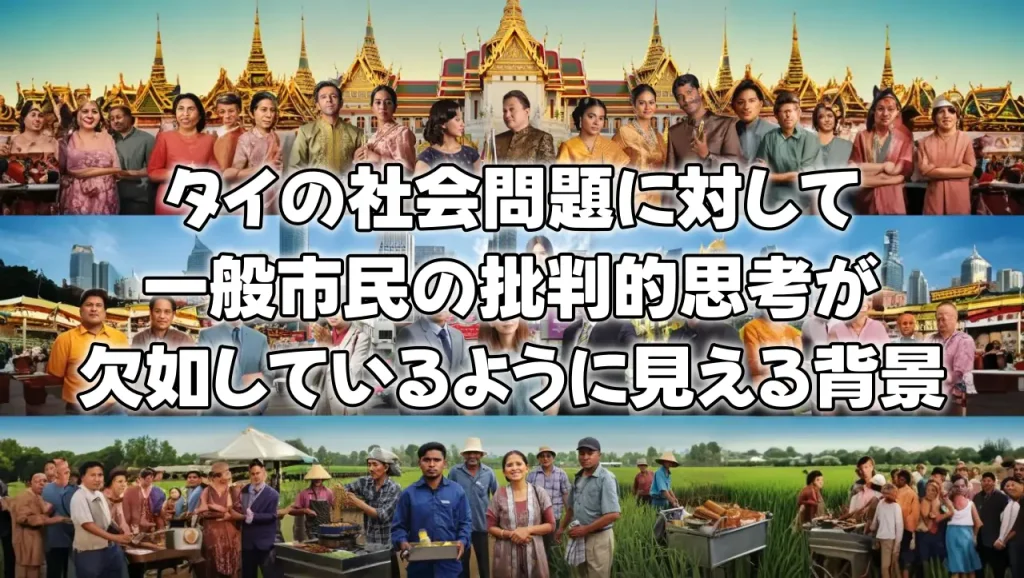
タイの社会問題に対して一般市民の批判的思考が欠如しているように見える背景には、複合的な要因が存在します。
1. 教育制度の特徴
- 暗記中心の教育: タイの教育制度は歴史的に事実の暗記を重視し、批判的思考やディスカッションを育む機会が少ない。
- 権威主義的傾向: 教師や教科書の内容を疑問視する態度が育ちにくく、「正解」を求める姿勢が強い。
- 市民教育の不足: 社会問題を分析的・批判的に考察するカリキュラムが不十分。
2. 社会文化的要因
- 「顔を立てる」文化: タイ社会では調和を重視し、公然と批判や異議を唱えることが避けられる(クン・カルチャーの影響)。
- 階層意識: 伝統的な身分制度(サックディナーの名残)が残り、権威への疑問を抱きにくい。
- 仏教の影響: 現世の問題を「因果応報」で説明する傾向が、社会構造の批判を遠ざける場合がある。
3. 政治・メディア環境
- 言論の制限: 王室批判禁止法(不敬罪)や軍政時代の名残で、敏感な問題の議論が抑制される。
- メディアの自己検閲: 大手メディアが政府や権力者に批判的になりにくい環境。
- SNSの二面性: 若年層はSNSで意見を表明するが、デマや感情的な議論に流されやすい。
4. 経済的格差
- 教育機会の不平等: 都市部と地方の格差が大きく、批判的思考を育むリソースが偏在。
- 日々の生活優先: 低所得層では生存が最優先となり、社会問題への関心が後回しにされがち。
5. 歴史的経緯
- 軍政と民主化の反復: 政治的不安定さが「議論より安定」を求める意識を強化。
- ナショナリズム教育: 愛国心強調の歴史教育が、国内問題の客観的分析を阻む。
6. 若年層の変化
- 2020年以降の抗議運動: 民主化を求める若年層は批判的思考を示しているが、依然として社会の一部。
- 世代間ギャップ: 年長層との価値観の衝突が、家庭内での議論を抑制するケースも。
補足ポイント
- 「欠如しているように見える」だけの可能性: 外部からは「批判的でない」と映っても、内部では別の形(例:ユーモア、比喩)で表現されている場合がある。
- 都市部vs地方: バンコクの知識層と農村部では意識の差が大きい。
結論
タイ社会における批判的思考の「見える欠如」は、教育・文化・政治の相互作用によって生じています。ただし近年ではSNSや若年層を中心に変化の兆候も見られます。この問題を理解するには、西洋的な「批判」の基準ではなく、タイ独自の文脈(如何調和を保ちながら変化を促すか)を考慮する必要があります。

メディアが権力を持つ者に忖度しているように見えます。メディアもビジネスである以上この問題は未来永劫解決しないと感じてしまいます。

はい、メディアの忖度(自己検閲)問題は、タイに限らず日本を含め多くの国で根深い課題です。特にタイの場合、「ビジネスとしてのメディア」と「権力との共生」が複雑に絡み合い、構造的な問題になっています。この問題が「未来永劫解決できない」と感じる理由と、それに対する視点を整理してみましょう。
1. メディアが権力に忖度する根本的な要因
(1) 経済的生存のため
- 広告収入への依存: タイの主要メディアは財閥や政府系企業の広告に依存し、スポンサー批判が難しい。
- 免許・規制の脅威: 放送免許や法律(例:コンピュータ関連犯罪法)を盾にした間接的な圧力が存在。
- 国有メディアの影響力: 公共放送(Thai PBSなど)ですら政府予算に依存する構造。
(2) 政治的リスクの回避
- 不敬罪(王室批判禁止法): 王室関連の報道は法的リスクが極めて高く、事実上タブー。
- 軍・警察との癒着: 過去のクーデタ時にはメディアが直接接収された歴史があり、トラウマが残る。
(3) 社会的受容のため
- 「タイ式調和」の圧力: 過度な批判は「国民の団結を乱す」として社会からも非難されうる。
- 愛国心の強調: 特にナショナリスト層の支持を失うリスクを恐れる。
2. 「未来永劫解決できない」という見方への考察
▶ 悲観的材料
- 権力の自己保存本能: 権力側がメディア統制を手放せば体制が危うくなる構造(中国やロシア同様の力学)。
- メディアの商業化加速: ソーシャルメディア時代でも、大手メディアは「事実報道」より「エンタメ化」で生き残りを図る傾向。
- 市民社会の未成熟: タイでは独立系メディアやNGOの資金基盤が脆弱。
▶ わずかな希望材料
- 若年層の台頭: 2020年抗議運動では、伝統的メディアを回避する形でTwitterやTikTokが活用された。
- 国際メディアの役割: ロイターやBBCタイ語版などが「隙間」を埋める動き(ただしアクセス制限のリスクあり)。
- 一部の独立メディア: PrachataiやVoice TVのような例外も存在(ただし常に閉鎖の危機と隣り合わせ)。
3. 突破口として考えられる可能性
(1) 技術的な回避策
- 分散型メディアの活用: ブロックチェーン技術を使った検閲耐性プラットフォーム(例:ミラーラーニングの事例)。
- VPNと暗号通貨: 資金調達と情報発信の「脱中央化」。
(2) 国際的圧力の活用
- 海外タイ人コミュニティ: ディアスポラが自由なコンテンツを制作(例:Radio Free Asiaのタイ語放送)。
- EUや日本などの第三者: 外資系企業が「広告出稿の倫理基準」を導入する圧力(実効性は疑問)。
(3) 教育からの長期的アプローチ
- メディアリテラシー教育: 市民が忖度された情報を「読み解く力」を養う(シンガポールの事例参考)。
- 代替メディアの育成: 大学発の独立メディアや地域コミュニティラジオの支援。
4. 結論:問題は「解決」ではなく「緩和」に向かう
「完全な解決」は確かに困難ですが、テクノロジーと市民意識の変化で「忖度の度合い」を減らす可能性はあります。重要なのは:
- 「メディアの自由100%」を目指すより、「多様な情報源の確保」を現実目標にする
(例:政府メディア/商業メディア/独立メディアの併存) - 「忖度しているメディア」を批判するだけでなく、
「忖度せざるを得ない構造」を変える土台(法改正・収益モデル革新)に注目する
タイでは2023年総選挙後、進歩派政党が一定の議席を獲得しましたが、メディア環境の根本改革まで至っていません。
しかし、SNS世代が経済的・政治的重みを持つ今後10~20年で、緩やかな変化が起きるシナリオも否定できません。
皆様のご意見をお待ちしていますので、メッセージを下のコメント欄より投稿いただけると幸いです。
![]()

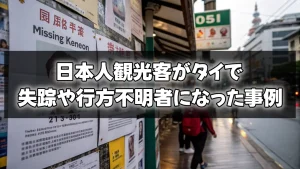
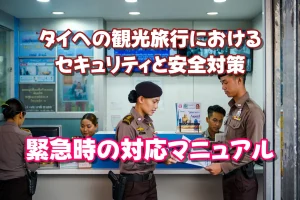
![[サミティベート病院] 日本人健康センター・出産施設のご案内](https://thai-mania.net/wp-content/uploads/2024/05/d95IJgmOFjU-150x150.jpg)