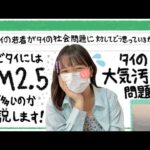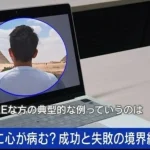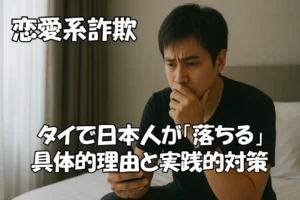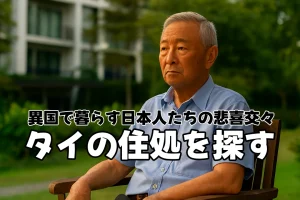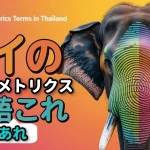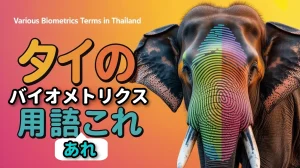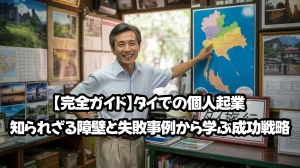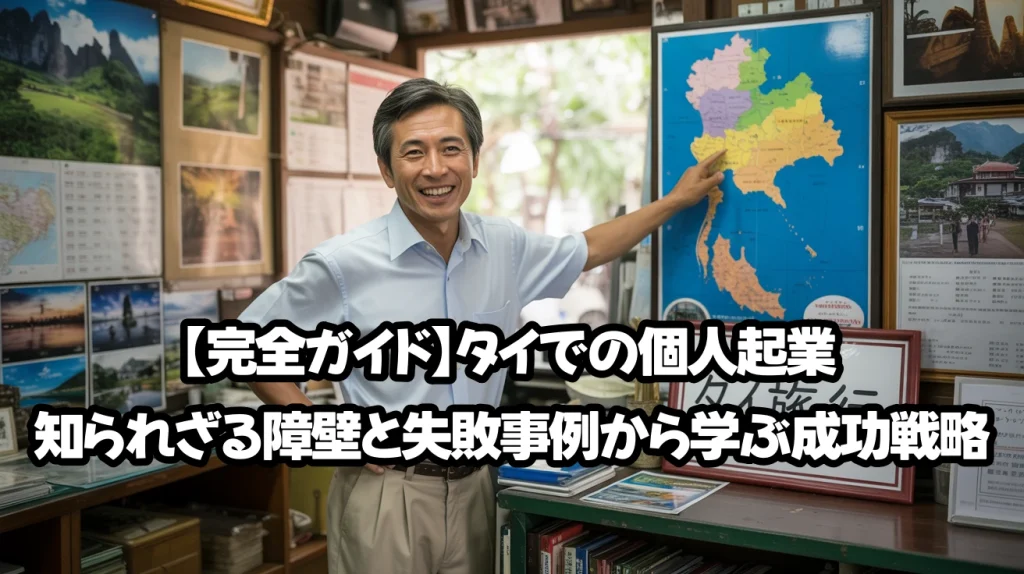
目次
- 記事の導入:なぜ今、タイでの起業が注目されるのか?その光と影
- 第一部:最大の難関「法規制と手続き」の壁
- 第二部:事業運営における「想定外」の失敗事例
- 第三部:障壁を乗り越えるための実践的ソリューション
- 結論:タイでの起業は「準備」が9割
記事の導入:なぜ今、タイでの起業が注目されるのか?その光と影
東南アジアの中心に位置し、「微笑みの国」として世界中の人々を魅了するタイ。その魅力は観光だけに留まりません。ASEAN創設メンバー国の一つとして、6億人を超える巨大市場へのゲートウェイとなる戦略的立地。約7,100万人の健全な消費者基盤と、豊富でコスト効率の高い労働力。そして、着実に進むインフラ整備と近代的なビジネス環境。これらの要素が融合し、タイは今、多くの外国人起業家にとって「チャンスの地」として熱い視線を集めています(TMF Group, 2024)。特に、政府が推進するデジタル経済政策「Thailand 4.0」は、AI、フィンテック、ヘルステックといった先端分野でのイノベーションを加速させ、スタートアップエコシステムは大きな活況を呈しています(International Trade Administration, 2024)。
しかし、この輝かしい光の裏には、特に経験の浅い外国人個人起業家を待ち受ける、深く、そして複雑な「影」が存在します。夢と希望を胸にタイの地に降り立ったものの、見えない障壁に阻まれ、志半ばで事業を断念するケースは後を絶ちません。その障壁とは、単なる言語や文化の違いといったレベルに留まらない、より構造的で根深い問題です。外国人としての事業活動を厳しく制限する法規制、迷宮のように入り組んだ行政手続き、そして日本とは全く異なる商習慣や市場力学。これらは、楽観的な見通しをいとも簡単に打ち砕く「落とし穴」となり得ます。
本稿では、タイでの個人起業を志す方々が、単なる夢物語で終わることなく、現実に根差した成功戦略を構築できるよう、徹底的なガイドを提供します。私たちは、インターネット上に散在する断片的な情報や成功体験談だけでなく、法務事務所の公式見解、政府機関の報告書、そして数々の失敗事例を丹念に分析しました。本稿を通じて、外国人起業家が直面する法規制、資金調達、文化、市場といった現実的な課題を一つひとつ解き明かし、それらを乗り越えるための具体的かつ実践的な「処方箋」を提示します。タイでの起業という挑戦が、無謀な賭けではなく、確かな知識に裏打ちされた戦略的な一歩となること。それが本稿の唯一の目的です。
第一部:最大の難関「法規制と手続き」の壁
タイでの起業において、外国人個人起業家が最初に、そして最も高くそびえ立つ壁として直面するのが、法規制と行政手続きの複雑さです。このセクションでは、事業の根幹を揺るがしかねない法的・制度的課題を、具体的な失敗のリスクと共に詳細に解説します。これらの知識なくして、タイでの事業成功はあり得ません。
外国人事業法(FBA)という「49%の壁」と名義貸しの罠
タイにおける外国人投資を規定する最も重要な法律が「外国人事業法(Foreign Business Act, B.E. 2542 (1999))」、通称FBAです。この法律の核心は、タイの国内産業を保護し、外国資本の無秩序な流入をコントロールすることにあります。外国人起業家にとって、FBAは事業の形態そのものを決定づける、避けては通れない規制です。
外国人事業法(FBA)の基本構造:49%の出資比率制限
FBAの最も根幹をなす規定は、原則として、外国資本がタイ法人の株式の過半数(50%以上)を保有することを制限している点です。つまり、外国人は会社の株式の最大49%までしか所有できず、残りの51%はタイ国籍の個人または法人が保有する必要があります(Siam Legal)。この「49%の壁」は、外国人起業家が自らの会社に対して完全な経営支配権を握ることを法的に困難にしています。この規制を回避するためには、後述するタイ投資委員会(BOI)の奨励を受けるか、外国人事業許可証(FBL)を取得するといった例外的な措置が必要となります。
事業活動を縛る「規制業種リスト」
FBAは、単に出資比率を制限するだけでなく、外国人が従事できる事業活動そのものを3つのリストに分類し、厳しく管理しています。これらのリストを理解することは、自らの事業計画がタイで実現可能かどうかを判断する第一歩です。
- リスト1:外国人による事業が絶対的に禁止される業種
国の根幹や文化に深く関わる事業が含まれます。例えば、新聞・ラジオ・テレビなどの報道事業、米作や畑作などの農業、天然林からの林業、タイの領海内での漁業、土地取引などが該当します(Thailand Law Library)。これらの業種は、特別な法律や条約による例外がない限り、外国人が参入することはできません。 - リスト2:内閣の承認が必要な業種
国家の安全保障、芸術文化、伝統工芸、天然資源などに影響を与える可能性のある事業が分類されます。武器・弾薬の製造、国内の陸運・水運・空運などがこれにあたります。これらの事業を外国資本が過半数を占める形で行うには、商務大臣の許可に加え、内閣による承認という非常に高いハードルを越える必要があります(モノリス法律事務所)。 - リスト3:外国人事業委員会の許可が必要な業種
「タイ国民が外国人との競争にまだ十分な準備ができていない」と見なされる事業分野です。会計サービス、法律サービス、建築サービス、エンジニアリングサービス、広告業、ホテル業(ホテル運営サービスを除く)、飲食料品の販売などが含まれます(Thailand Law Library)。多くのサービス業がこのリストに該当するため、個人起業家が検討するビジネスモデルの多くが、このリスト3の規制対象となる可能性があります。これらの事業を外資過半数で行うには、外国人事業委員会の審査を経て、事業開発局長から「外国人事業許可証(FBL)」を取得しなければなりません。
【最重要・失敗事例】:「ノミニー(名義貸し)」という破滅への近道
この厳格な49%規制を回避するための「裏技」として、長年にわたり横行してきたのが「ノミニー(Nominee)」、すなわちタイ人の名義を借りて会社を設立する行為です。これは、実質的な経営権や資金は外国人投資家が握りながら、書類上はタイ人が51%の株主であるかのように装う手口です。友人、恋人、あるいは紹介されただけのタイ人に名義を借り、実態は100%外資でありながら、規制を免れようとします。
しかし、この行為は明確な違法行為であり、タイ当局は近年、観光業や不動産業を中心に、このノミニー構造に対する取り締まりを大幅に強化しています(note.com, 2025)。安易な名義貸しの利用が、いかに深刻なリスクを伴うかを理解しなければなりません。
One of the most significant challenges of doing business in Thailand is the ownership restrictions imposed by the Foreign Business Act (FBA)... It is essential to note that using Thai nominee shareholders to circumvent these restrictions is illegal and can result in hefty fines or imprisonment.
— Herrera & Partners, 2024
名義貸しが発覚した場合のリスクは、事業の存続を不可能にするほど壊滅的です。
- 刑事罰:名義を借りた外国人経営者だけでなく、名義を貸したタイ人にも、高額な罰金や禁固刑が科される可能性があります。
- 事業停止と資産没収:会社は解散を命じられ、事業を通じて得た利益や資産が没収されるリスクがあります。
- 名義人による裏切り:法的には、会社の過半数の株式と議決権は名義人であるタイ人が保有しています。関係が悪化した場合、名義人が突然「自分こそが会社の所有者だ」と主張し、会社の資産や銀行口座を支配し、経営権を乗っ取るという事例は枚挙にいとまがありません。この場合、違法行為に加担している外国人側は法的な保護を求めることが極めて困難になります。
- 税務上の追徴課税:脱税の疑いをかけられ、過去に遡って多額の追徴課税を請求される可能性もあります(note.com, 2025)。
「みんなやっているから大丈夫」という甘い考えは通用しません。タイでのビジネスを長期的に、そして合法的に成功させたいのであれば、ノミニーの利用は絶対に避けるべき選択肢です。それは成功への近道ではなく、破滅への入り口に他なりません。
キーポイント:法規制の壁
- 49%の壁:外国人事業法(FBA)により、原則として外国人の株式保有は49%までに制限される。
- 規制業種:メディア(禁止)、サービス業(許可制)など、事業内容によって厳しい制限が存在する。
- ノミニーの罠:タイ人名義を借りる行為は違法であり、発覚すれば禁固刑、資産没収、事業停止など壊滅的なリスクを伴う。安易な選択は絶対に避けるべきである。
迷宮のような会社設立プロセスと煩雑な手続き
外国人事業法の壁を認識した上で、次に待っているのが、タイの株式会社(Private Limited Company)を設立するための具体的な手続きです。一見すると、プロセスは標準的に見えますが、その裏には外国人起業家を悩ませる数々の「障壁」が潜んでいます。
会社設立の基本ステップ
日本の法務局(JETRO)や現地の法律事務所の情報によると、タイでの会社設立は、一般的に以下の4つのステップで進められます(JETRO, 2024)。
- 商号の予約(Company Name Reservation):まず、商務省事業開発局(DBD)のウェブサイトまたは窓口で、希望する会社名を3つまで提案し、予約します。既存の会社名と類似していないか、規制に違反していないかなどが審査され、承認された商号は30日間有効となります。
- 基本定款の登記(Filing of Memorandum of Association):商号が予約できたら、会社の基本情報(会社名、資本金の額、事業目的、発起人の情報など)を記載した基本定款を作成し、DBDに登記します。この時点で最低2名(以前は3名)の発起人が必要です(Acclime Thailand, 2025)。
- 設立総会の開催(Statutory Meeting):基本定款の登記後、発起人は設立総会を招集します。この会議で、株式の引き受け、取締役の選任、監査人の選任、会社の付属定款の承認など、会社の運営に関する重要事項を決定します。
- 会社設立登記(Company Registration):設立総会から3ヶ月以内に、選任された取締役がDBDに最終的な会社設立登記を申請します。この時点で、株主は引き受けた株式の代金を少なくとも25%払い込む必要があります。すべての書類が受理されれば、会社設立は完了し、法人番号が発行されます。その後、60日以内に税務IDを取得し、必要に応じて付加価値税(VAT)の事業者登録を行います。
【障壁・問題点】手続きに潜む3つの「壁」
この一連の流れは、文字で追うだけではその困難さが伝わりにくいかもしれません。しかし、実際に外国人起業家がこのプロセスに挑むと、以下のような現実に直面します。
1. 書類の壁:タイ語のジャングル
会社設立に必要な申請書類、定款、議事録など、DBDに提出する公式書類は、そのほとんどがタイ語で作成されなければなりません(Siam Legal)。法律用語や会計用語が多用されるこれらの書類を、タイ語に不慣れな外国人が独力で正確に作成することは、事実上不可能です。些細な記入ミスや翻訳の不備が、申請の却下や手続きの大幅な遅延につながるため、信頼できるタイ語話者、理想的には現地の法律専門家の支援が不可欠となります。
2. 時間の壁:予測不能な「官僚主義(レッドテープ)」
タイの行政手続きは、しばしば「レッドテープ(Red Tape)」と形容される、非効率で時間のかかる官僚主義的な側面を持っています(Thai PBS World, 2025)。DBDはプロセスのデジタル化を進めていますが、依然として物理的な署名や対面での本人確認が必要な場面が多く、複数の政府機関(商務省、歳入局、社会保険事務所など)を何度も往復しなければならないことも珍しくありません。申請から承認までにかかる時間は担当官の裁量や窓口の混雑状況によって大きく変動し、「1ヶ月〜1ヶ月半程度」という一般的な目安(JETRO, 2024)を大幅に超えることも覚悟しておく必要があります。この予測不能な遅延は、事業開始のスケジュールを狂わせ、機会損失に直結します。
3. 資本金の壁:外国人雇用に伴う負担
タイの会社法自体には、最低資本金の厳格な規定はありません。しかし、外国人としてタイで働き、労働許可証(ワークパーミット)を取得するためには、別の法律が適用されます。原則として、外国人従業員1名を雇用するごとに、会社は最低200万バーツ(約800万円 ※1バーツ=4円換算)の払込済資本金を登録する必要があります(JETRO, 2024)。つまり、起業家自身がタイで働く場合、会社は最低でも200万バーツの資本金を用意しなければならないのです。これは、スモールスタートを目指す個人起業家にとって、決して小さくない初期投資のハードルとなります。さらに、事業内容がFBAの規制対象業種に該当する場合は、最低資本金が300万バーツに引き上げられることもあります(Law.asia, 2023)。
これらの壁は、タイでの起業が単なるアイデアや情熱だけでは乗り越えられない、専門知識と十分な準備資金を要する厳しい挑戦であることを物語っています。
就労ビザと労働許可証(ワークパーミット)という二重の関門
会社設立というハードルを越えても、外国人起業家がタイで合法的に働くためには、さらに二つの重要な許可を取得しなければなりません。それが「就労ビザ(Non-Immigrant Visa "B")」と「労働許可証(Work Permit)」です。この二つは密接に関連しながらも、管轄が異なり、それぞれが独立した申請プロセスを持つため、多くの外国人を混乱させる「二重の関門」となっています。
切り離された二段階プロセス
タイで働くための手続きは、以下の二段階で進めるのが一般的です。この順番を間違えると、タイに入国できない、あるいは入国できても働くことができないという事態に陥ります。
- ステップ1:タイ国外での「ノンイミグラント-Bビザ」の取得
まず、就労を目的としてタイに入国するための査証(ビザ)である「ノンイミグラント-Bビザ」を、自国(日本など)にあるタイ王国大使館または総領事館で申請・取得する必要があります(Mitsuki Japan, 2025)。このビザは、タイで働く「資格」を得るための入場券のようなもので、通常90日間の滞在が許可されます。申請には、タイで設立した会社からの招聘状や会社の登記簿謄本など、雇用主となる会社側が用意する書類が多数必要となります。 - ステップ2:タイ入国後の「労働許可証(ワークパーミット)」の申請
ノンイミグラント-Bビザでタイに入国した後、速やかに労働省雇用局に「労働許可証(ワークパーミット)」を申請します。この許可証があって初めて、タイ国内で具体的な労働活動(経営活動を含む)を行うことが法的に許可されます(ThaiEmbassy.com)。たとえ就労ビザを持っていても、ワークパーミットなしで働くことは不法就労と見なされ、罰金や国外退去処分の対象となります。ワークパーミットの申請・取得には、通常7営業日から数週間かかるとされています。
このプロセス全体を完了し、1年間の滞在許可を得るためには、ワークパーミット取得後に再度入国管理局でビザの延長手続きを行う必要があり、非常に煩雑です。
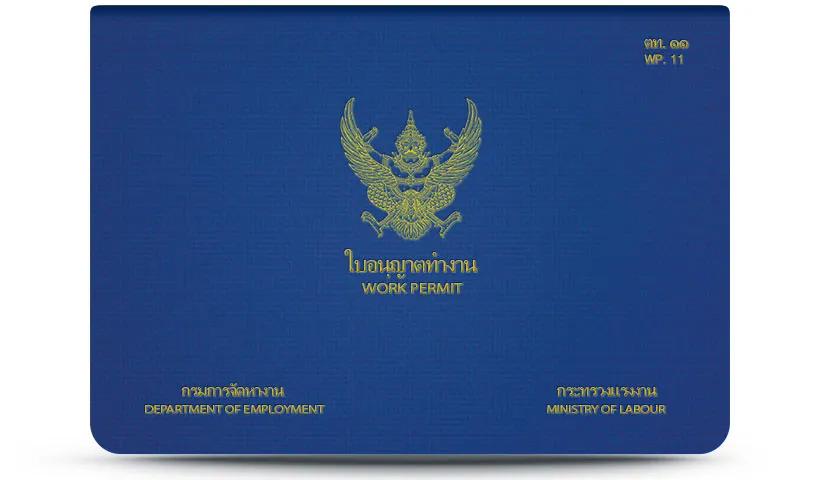
【障壁・問題点】厳格な発行要件と不確実性
この二重の関門には、外国人起業家を阻む数々の厳しい条件と運用上の問題が存在します。
1. 厳格な発行要件(資本金とタイ人雇用)
前述の通り、ワークパーミットの発行には、会社が一定の条件を満たしている必要があります。最も代表的なものが以下の2つです。
- 資本金:外国人1名につき、最低200万バーツの払込済資本金。
- タイ人従業員比率:原則として、外国人1名につき、4名のタイ人従業員を雇用し、社会保険に加入させていること(Adecco Thailand, 2025)。
これらの要件は、事業がまだ軌道に乗っていない設立初期のスタートアップにとって、極めて重い経済的負担となります。4人のタイ人従業員を雇用する人件費と社会保険料、そして200万バーツの資本金は、多くの個人起業家の計画を頓挫させるに十分なインパクトを持ちます。
2. 職務内容の合理性
申請時には、「なぜその職務をタイ人ではなく、その外国人が行う必要があるのか」という合理的な説明が求められます。申請する職務内容が、タイ人では代替が難しい専門的な知識やスキルを要するものであることを、説得力をもって示す必要があります(Siam Legal)。曖昧な職務内容では、申請が却下される可能性があります。
3. 不確実性と非効率性
すべての書類と条件を整えても、ワークパーミットの承認は保証されていません。審査は労働局の担当官の裁量に委ねられる部分が大きく、同じ申請内容でも担当官によって判断が異なることさえあります。また、審査期間も「原則3労働日」(Lean Operation, 2025)とされながらも、実際にはそれ以上かかることが多く、その間の不確実性は精神的な負担となります。さらに、取得したワークパーミットは、許可された特定の会社、職務内容、勤務地でのみ有効です。もし将来、事業拡大に伴いオフィスを移転したり、職務内容を変更したり、あるいは別の会社を立ち上げたりする場合には、その都度、変更申請や新規申請という煩雑な手続きをやり直さなければなりません(Herrera & Partners, 2024)。
このように、法規制と手続きの壁は、タイでの起業を志す者にとって、時間、費用、そして精神力を大きく消耗させる最初の、そして最大の試練なのです。
第二部:事業運営における「想定外」の失敗事例
複雑な法的手続きを乗り越え、ようやく事業を開始できたとしても、安心はできません。次に待ち受けるのは、タイ特有の市場環境と文化の壁です。多くの外国人起業家が、自国での成功体験やビジネスの常識が通用しない現実に直面し、「想定外」の失敗に陥ります。このセクションでは、実際の企業事例を基に、運営段階で陥りがちな失敗パターンを分析し、その教訓を探ります。
「郷に入っては郷に従えず」- 文化・言語の壁による失敗
タイでのビジネスにおいて、最も見過ごされがちでありながら、最も根深い問題の一つが文化とコミュニケーションスタイルの違いです。特に、個人起業家として現地スタッフを率い、取引先と交渉する立場にある外国人経営者にとって、この壁は事業の成否を左右する致命的な要因となり得ます。
コミュニケーションの断絶を生む文化的背景
タイの職場文化や商習慣には、日本や欧米とは異なる独特の価値観が根付いています。これらを理解しないまま、自国のスタイルを押し通そうとすると、深刻な摩擦や誤解が生じます。
- 階層意識と敬意:タイ社会は年長者や役職が上の人物を敬う階層意識が強く、部下が上司に直接的な反論や意見を述べることは稀です。このため、外国人経営者が「なぜ誰も意見を言わないんだ」と苛立っても、それは部下の無能さや意欲の欠如ではなく、文化的な配慮の表れであることが多いのです(JacksonGrant)。
- 間接的なコミュニケーションと「クレンチャイ(Kreng Jai)」:タイ人は相手の気持ちを過度に配慮し、対立を避けるために「No」をはっきり言わない傾向があります。この「クレンチャイ」という文化は、相手を困らせたり、恥をかかせたりすることを恐れる心遣いです。しかし、ビジネスの現場では、これが問題の先送りや意図の誤解につながります。例えば、部下はできない仕事でも「できます」と答えてしまい、後になって納期に間に合わないことが発覚する、といったケースです。
- 言語の壁:バンコクなどの都市部では英語が通じる場面も多いですが、政府機関の書類はタイ語が基本であり、地方や特定の業界では英語の通用度が著しく低下します(Herrera & Partners, 2024)。微妙なニュアンスが伝わらないことで、契約内容の誤解や指示の不徹底といった問題が頻発します。
【失敗事例】文化摩擦が引き起こす事業の停滞
これらの文化的な違いは、具体的なビジネス上の失敗として現れます。
- 従業員マネジメントの失敗:直接的で厳しいフィードバックに慣れている外国人経営者が、タイ人スタッフに対して同じように接した結果、スタッフはプライドを傷つけられたと感じ、モチベーションを失い、最終的に離職してしまう。特に優秀な人材ほど、より良い職場環境を求めて転職する傾向が強く、結果として組織全体の生産性が低下し、人材の定着に苦しむことになります(タイ人採用でよくある3つの失敗と対策マニュアル)。
- 商談・交渉の失敗:タイのビジネスでは、契約内容そのものよりも、まず相手との個人的な信頼関係を構築することが重視されます。食事を共にしたり、雑談を交わしたりする時間を軽視し、性急にビジネスの本題に入ろうとすると、「信頼できない相手」と見なされ、交渉がうまくいかなくなることがあります。相手の曖昧な返事を「合意」と捉えてしまい、後になって話が覆されるというのも典型的な失敗パターンです。
これらの失敗を避けるためには、経営者自身がタイの文化を学ぶ努力をすることはもちろん、重要なコミュニケーションには信頼できるバイリンガルスタッフや通訳を介在させること、そして異文化理解のための研修を導入するなど、組織的な対策が不可欠です。文化の壁は、単なる「慣れ」の問題ではなく、戦略的に乗り越えるべき経営課題なのです。
「本国では成功したのに…」- 市場理解の欠如とローカライズの失敗
自国で成功を収めたビジネスモデルやマーケティング戦略が、他の国でも同じように通用するとは限りません。特に、消費者行動や市場構造が独特なタイにおいては、「ローカライズ(現地化)」の失敗が事業の命運を分けることが多々あります。ここでは、世界的な大企業の事例から、その教訓を学びます。
【ケーススタディ1:Uberの敗北】地域チャンピオンに敗れたグローバル企業の教訓
ライドシェアサービスの巨人であったUberは、タイ市場から事実上撤退し、東南アジア事業を地域最大の競合であるGrabに売却しました。この敗北の背景には、グローバルで標準化された戦略と、タイ市場の現実に即したローカライズ戦略との間の決定的な差がありました。
Uber failed because it faced competition from a regional competitor who was better adapted to and able to respond more quickly to conditions and changes in the Thailand market.
— Aaron Henry on LinkedIn, 2019
GrabがUberに勝利した要因は、徹底したローカライズにありました。
- 決済方法の多様性:Uberがクレジットカード決済を基本としていたのに対し、Grabは現金払いを早期から導入しました。クレジットカード保有率がまだ高くないタイ市場において、この差は決定的でした。さらに、GrabはTrueMoney Walletのような現地の電子マネー決済にも積極的に対応し、利便性を高めました。
- サービスの多様化:Grabは配車サービスだけでなく、バイクタクシー(GrabBike)やフードデリバリー(GrabFood)、荷物配送(GrabExpress)など、現地のニーズに合わせた多様なサービスを次々と展開し、人々の生活に深く浸透する「スーパーアプリ」としての地位を確立しました。
- ドライバーとの関係構築:Grabは、ドライバーに対して車両のリースや融資プログラムを提供するなど、単なるプラットフォーム提供者以上の関係を築き、安定したドライバー網を確保しました(LinkedIn)。
Uberの失敗は、優れたテクノロジーやグローバルなブランド力だけでは、地域に深く根差した競合には勝てないという厳しい現実を突きつけています。現地の消費者が何を求め、どのような支払い方法を好み、どんな生活をしているのか。その解像度の高さが勝敗を分けたのです。
【ケーススタディ2:コカ・コーラの苦戦】グローバル広告が響かなかった理由
世界的なブランドであるコカ・コーラも、タイ市場で苦戦した時期がありました。その原因は、グローバルで展開される広告キャンペーンを、大きな変更なしにタイで放映したことにありました。タイのマーケティング専門家は、「タイの若者がコカ・コーラに期待するのは『若々しい精神』『クールさ』『ヒップさ』だが、長年、同社は新製品やインパクトのあるキャンペーンで市場を興奮させてこなかった」と指摘しています(IIBS Bangalore, 2024)。グローバルで統一されたメッセージは、タイの若者の心には響かず、ブランドイメージの陳腐化を招きました。この事例は、たとえ世界最強のブランドであっても、現地の文化や消費者の感性に合わせたマーケティングの調整、すなわち「広告のローカライズ」が不可欠であることを示しています。
教訓:タイ市場の特性を理解する
これらの失敗事例から、外国人起業家が学ぶべき教訓は明確です。自国の成功体験を過信せず、タイ市場のユニークな特性を深く理解する必要があります。
- 強い価格志向:タイの消費者は価格に非常に敏感です。特に日用品や食品においては、低価格輸入品やローカルブランドとの厳しい競争にさらされます(International Trade Administration, 2024)。単に高品質であるだけでは不十分で、価格に見合う価値(Value for Money)をいかに提供できるかが鍵となります。
- キャッシュレス決済の急速な普及:近年、タイではQRコード決済を中心にキャッシュレス化が爆発的に進んでいます。Visaの調査によれば、消費者の8割以上が普段は現金を使わない「キャッシュレス生活」を送っていると報告されています(WiSE, 2024)。多様な決済手段、特にPromptPayやTrueMoney Walletといったローカルの決済サービスへの対応は、もはや必須条件です。
- 口コミとインフルエンサーの影響力:タイでは、友人や家族からの口コミ、そしてソーシャルメディア上のインフルエンサーのレビューが、消費者の購買決定に絶大な影響を与えます。マス広告よりも、信頼できる個人からの情報が重視される傾向が強いです。
事業を始める前に、徹底的な市場調査を行い、ターゲット顧客の行動や価値観を深く洞察すること。そして、製品、価格、プロモーション、販売チャネルのすべてにおいて、タイ市場に最適化された戦略を構築すること。これこそが、ローカライズ失敗の轍を踏まないための唯一の道です。
「ヒト・モノ・カネ」の現実 - スタートアップが直面する資源不足
素晴らしいビジネスアイデアと市場への深い理解があっても、それを実行するための資源、すなわち「ヒト(人材)」「モノ(インフラ等)」「カネ(資金)」がなければ、事業は成長できません。特に、まだ基盤の弱いスタートアップにとって、これらの資源不足は深刻な足かせとなります。
1. 人材獲得の困難:「スキル」と「コスト」のジレンマ
事業の成長を牽引するのは、言うまでもなく優秀な人材です。しかし、タイで外国人起業家が理想的なチームを構築する道のりは平坦ではありません。
- 優秀なバイリンガル人材の争奪戦:タイ語と英語(あるいは日本語)の両方に堪能で、かつ専門スキルを持つ人材は非常に貴重です。こうした人材は、外資系大企業や待遇の良い地元大手企業からの需要も高く、常に激しい争奪戦が繰り広げられています。結果として、彼らの給与水準は他の東南アジア諸国と比較して高くなる傾向にあり、資金力の乏しいスタートアップにとっては大きな負担となります(Herrera & Partners, 2024)。
- スキルのミスマッチ:政府は「Thailand 4.0」政策の下でSTEM(科学・技術・工学・数学)分野の人材育成に力を入れていますが、依然として多くの卒業生が専門分野とは異なる職に就いているという現実があります(SCB 10X, 2025)。そのため、特に高度な技術を要する分野では、即戦力となる人材を見つけるのが難しい場合があります。
- 定着率の問題:前述の文化的な壁に加え、外国人経営のスタートアップは、キャリアパスの不透明さや福利厚生の未整備などから、従業員の定着率が低くなる傾向があります。高いコストをかけて採用した人材がすぐに辞めてしまうことは、事業にとって大きな損失です。
2. 資金調達の壁:発展途上のベンチャーキャピタル市場
事業をスケールさせるためには、外部からの資金調達が不可欠です。タイのスタートアップエコシステムは近年目覚ましい成長を遂げ、政府や大企業による支援も活発化していますが、資金調達環境、特にアーリーステージにおいては、依然として課題が残ります。
The Thai startup ecosystem is still in its developmental phase, and although it has produced some notable successes, it lags behind countries like Singapore or Hong Kong in terms of available venture capital and investment networks.
— Y-Consulting on Medium, 2024
タイの資金調達環境には、以下のような特徴があります。
- 限定的なアーリーステージ投資:シード期やシリーズAといった初期段階のスタートアップを支援する国内のベンチャーキャピタル(VC)の数は、東南アジアのハブであるシンガポールと比較するとまだ限られています。これにより、多くのタイのスタートアップは外国からの投資に大きく依存せざるを得ない状況です(SCB 10X, 2025)。
- CVC(コーポレートVC)の存在感:タイのVC市場は、大手財閥系企業などが設立したコーポレート・ベンチャーキャピタル(CVC)が大きな存在感を放っています。彼らは自社の既存事業とのシナジーを重視する傾向が強く、必ずしもすべての革新的なアイデアが投資対象となるわけではありません。
- 地域内での競争激化:近年、投資家はシンガポールだけでなく、タイ、インドネシア、ベトナムといった他のASEAN諸国にも目を向けており、投資資金の獲得競争は地域全体で激化しています(aboveA, 2025)。
とはいえ、悲観的な情報ばかりではありません。2025年の予測では、タイのスタートアップが調達する初期ラウンドの規模は以前よりも大きくなっており、平均的なシード資金は50万ドルから150万ドル、シリーズAラウンドは300万ドルから800万ドルに達すると報告されています(aboveA, 2025)。市場は確実に成長していますが、外国人起業家は、資金調達には多大な労力と時間、そして強力なネットワークが必要であるという現実を認識しておく必要があります。
人材不足と資金難は、事業の成長スピードを直接的に鈍化させ、競合他社に市場を奪われる原因となります。これらの資源をいかに戦略的に確保していくかが、スタートアップの生存と成長の鍵を握っているのです。
![]()