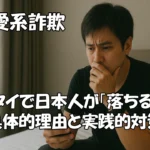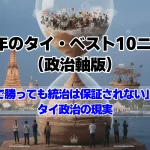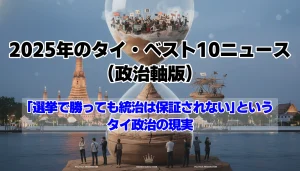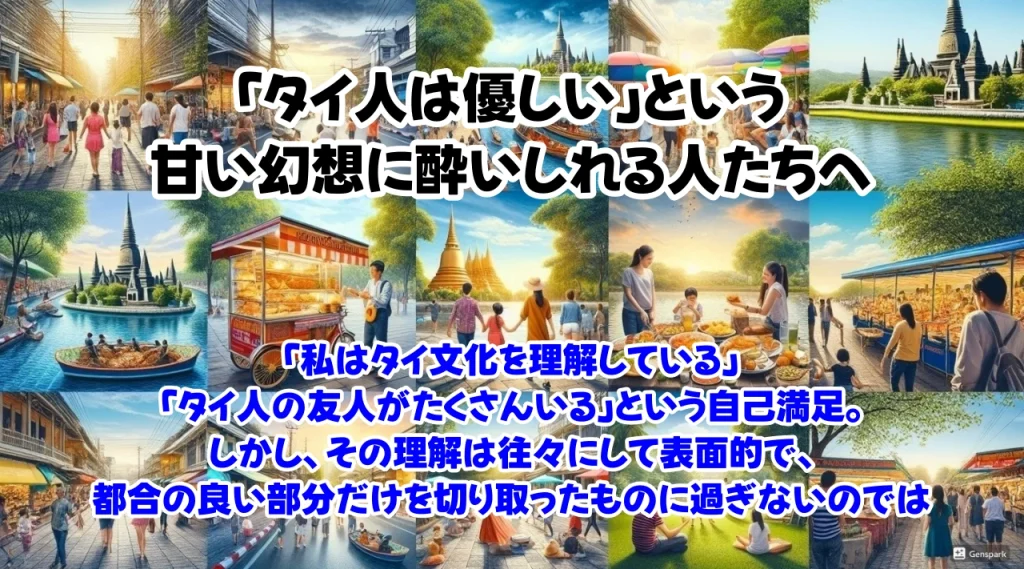
プロローグ:SNSの「タイ愛」投稿を見るたびに思うこと
「タイ人って本当に優しいよね〜」「みんな笑顔で最高!」「日本人も見習うべき!」
SNSを開けば、こんな投稿が毎日のように流れてくる。バンコクの屋台で撮った写真に添えられた感動的なエピソード、象とのツーショットの横に書かれた「心温まる交流」の話。見ているこちらが恥ずかしくなるほどの「タイ愛」溢れる投稿の数々。
でも、ちょっと待ってほしい。本当にそんなに単純な話なのだろうか?
第一章:観光地の「優しさ」という名の商品
まず理解すべきは、多くの日本人が体験する「タイ人の優しさ」は、実は高度に商品化されたサービスだということだ。
バンコクの観光地で働く人々にとって、外国人観光客への「優しさ」は文字通り飯の種である。カオサン通りの屋台のおばちゃんが日本語で「おいしいよ〜」と笑顔で声をかけてくるのは、確かに微笑ましい光景だ。しかし、その笑顔の裏には「この日本人からいくら売上が見込めるか」という冷静な計算が働いている。
これは決して悪いことではない。むしろ、プロフェッショナルな接客態度として評価されるべきだろう。問題は、それを「タイ人の民族性」として解釈してしまう日本人の思考回路にある。
同じ屋台のおばちゃんが、地元のタイ人客にはそっけない態度を取っていることを知っている日本人がどれだけいるだろうか? 外国人価格と地元価格の違いを「文化の違い」として受け入れる寛容さを持つ日本人観光客がどれだけいるだろうか?
第二章:「クレンチャイ」という美しい誤解
タイ文化を語るときによく登場する「クレンチャイ」という概念。「他者への思いやり」「相手の気持ちを察する」といった美しい意味で紹介されることが多い。
確かに、クレンチャイは素晴らしい文化的価値観だ。しかし、それが常に「優しさ」として現れるわけではない。時には、本音を言わない、はっきりと断らない、という形で表現されることもある。
例えば、タイ人の友人に「明日、一緒に映画を見に行かない?」と誘ったとき、「いいね、考えてみる」という返事が返ってきたとする。日本人の多くは「前向きに検討してくれている」と解釈するだろう。しかし、タイ社会では、これは丁寧な断り文句である可能性が高い。
相手を傷つけないように、直接的な拒否を避ける。これもクレンチャイの表れだが、日本人には「優しさ」として映る。一方、タイ人同士であれば、この微妙なニュアンスを理解し、それ以上追求しない。
文化的な配慮を「優しさ」と勘違いし、何度も同じ誘いを繰り返す日本人。そんな空気の読めない外国人に対して、タイ人がどんな感情を抱くか想像してみてほしい。
第三章:階層社会の現実と「優しさ」の使い分け
タイ社会を理解する上で避けて通れないのが、根深い階層意識だ。
日本人観光客が体験する「優しさ」の多くは、実は階層関係に基づいている。外国人、特に経済的に豊かとされる日本人は、一種の「お客様」として扱われる。これは敬意の表れでもあるが、同時に距離を置かれていることの表れでもある。
タイ人同士の関係では、年齢、社会的地位、経済力によって、態度や言葉遣いが明確に変わる。年上や地位の高い人に対しては恭しく、年下や地位の低い人に対しては時として高圧的になることもある。
コンドミニアムの警備員に対する態度、メイドさんへの接し方、レストランのウェイターとの関係。これらを観察すれば、「タイ人は優しい」という一般化がいかに表面的なものかがわかる。
もちろん、これはタイ社会だけの問題ではない。どの社会にも階層意識は存在する。しかし、「タイ人は優しい」という幻想に酔いしれている人々は、こうした複雑な社会構造を見ようとしない。
第四章:個人差という当たり前の事実
「タイ人は優しい」という言説の最大の問題は、6,500万人のタイ人を一括りにして語ろうとすることだ。
当たり前の話だが、タイ人にも様々な人がいる。親切で心優しい人もいれば、冷たくて利己的な人もいる。陽気で社交的な人もいれば、内向的で人見知りの人もいる。
バンコクの高級デパートで働く洗練された販売員と、イサーン地方の農村で暮らす素朴な農民を同じ「タイ人」として語ることに、どれだけの意味があるだろうか?
チュラロンコーン大学を卒業した都市部のエリートと、中学校も満足に卒業できなかった地方出身の工場労働者が、同じ価値観や行動様式を持つと考えるのは、あまりに単純すぎる。
それでも、「タイ人は優しい」という魔法の言葉を唱えることで、複雑な現実を単純化し、理解した気になれる。これほど都合の良い思考法があるだろうか?
第五章:「お花畑思考」の心理的メカニズム
なぜ日本人は「タイ人は優しい」という幻想に惹かれるのか?
一つには、日本社会に対する不満の裏返しがある。「日本人は冷たい」「ギスギスした社会だ」という現状認識があるからこそ、タイ社会が理想郷として映る。
もう一つは、異文化体験における優越感だ。「私はタイ文化を理解している」「タイ人の友人がたくさんいる」という自己満足。しかし、その理解は往々にして表面的で、都合の良い部分だけを切り取ったものに過ぎない。
さらに、SNS時代の承認欲求も関係している。「タイ人は優しい」という投稿は、多くの「いいね」を獲得しやすい。異論を唱える人は少なく、共感を得やすい安全な話題だからだ。
こうした心理的な要因が重なり合って、「お花畑思考」は再生産され続ける。
第六章:真の国際理解とは何か
本当の国際理解とは、相手の文化や社会を美化することではない。その複雑さ、矛盾、問題点も含めて受け入れることだ。
タイ社会には確かに素晴らしい面がある。家族を大切にする文化、宗教的な寛容さ、困っている人を助ける伝統。しかし同時に、汚職の蔓延、環境破壊、格差の拡大といった問題も存在する。
「タイ人は優しい」という一面的な見方では、こうした複雑な現実を理解することはできない。むしろ、現地に住む人々の真の苦労や努力を見えなくしてしまう。
エピローグ:幻想から現実へ
28年間バンコクに住んでいて思うのは、タイ人も日本人も、結局は同じ人間だということだ。優しい人もいれば、そうでない人もいる。親切な人もいれば、冷たい人もいる。
大切なのは、国籍や民族ではなく、一人ひとりの個人として相手を見ることだ。先入観や偏見を持たずに、その人自身と向き合うことだ。

真の友情や理解は、美化された幻想からではなく、ありのままの現実を受け入れることから始まる。それが、本当の意味での国際交流というものではないだろうか。
「タイ人は優しい」という甘い幻想に酔いしれるのは、もうやめにしよう。現実はもっと複雑で、だからこそもっと面白い。
皆様のご意見をお待ちしていますので、メッセージを下のコメント欄より投稿いただけると幸いです。

〇〇✗✗
〇〇✗✗
皆様のご意見をお待ちしていますので、メッセージを下のコメント欄より投稿いただけると幸いです。
![]()